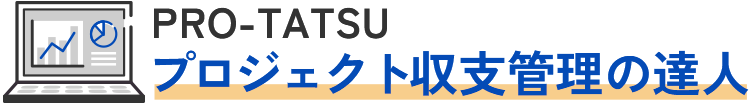ITサービスの価格戦略・値段の付け方
公開日:|更新日:
このページでは、ITサービスを提供するにあたってどのようなポイントや基準にもとづいて値段を設定すれば良いのか、価格戦略の基本について分かりやすく解説しています。自社のITサービスの料金設定を適正化してプロジェクトの収支管理をマネジメントしていくためにも、価格戦略を理解して明確な値段の付け方を把握しておきましょう。
価格戦略の重要性
価格戦略とは、自社のサービスや商品に関する料金設定や値段設定を適正化していくための考え方であり、適切な収支管理を実践して利益追求していくためのビジネス戦略でもあります。
価格戦略がしっかりと構築され、さらに実践されていなければ、サービスを提供しても消費者から利用されなかったり、利用者が多いのに思ったような利益を獲得できなかったりといったデメリットが増大します。そのため、ITサービスを提供する上でも価格戦略を構築して実践していくことが重要です。
ITサービスの値段を決める要素
新しく提供するITサービスや、リニューアルしたITサービスの値段を決定する上で、どのようなポイントを考慮して金額をシミュレーションしていけば良いのでしょうか。
ここでは自社が提供するITサービスの価格戦略や値段設定をプランニングしていくにあたって、代表的かつ重要なポイントをまとめましたのでぜひ参考にしてください。
原価率
原価率とは、売上高の中で原価が占める割合であり、原価率が高くなればなるほど利益として得られる金額は低下していきます。
ITサービスの原価率では、ITシステムを構築するエンジニアの労務費や専門企業へのアウトソーシング費用といったコストが大部分を占めており、それらの費用について全体像を把握しておかなければ原価率を計算することもできません。
あらかじめ想定する原価率を決定していれば、実際の原価をベースとして料金設定を進めることも可能です。
ただし、原価として計算すべきコストには直接的に関与しているものと間接的に関与しているものがあり、その区分を明確化しておくことも重要です。
利益率
原価率に対して、利益率とは売上高の中で利益として得られる割合であり、利益率が高いほどサービス提供の直接的なメリットも増大していくと考えられます。
ただし、実際には利益率といっても粗利にもとづくものや、税金などの諸経費を差し引いて最終的に残存する金額にもとづくものなど複数の種類があり、さらに業界や業種によって目安となる利益率が異なる点にも注意しなければなりません。そのため、適切な利益率を算出するためにも、同類や近しいITサービスの平均利益率などを調査することも大切です。
ITサービスの提供・販売形式
ITサービスを提供する場合、ITツールをパッケージングしてシステムそのものを売却する買い切り型と、システムの運用ベースを自社管理した上でユーザーはオンラインでITサービスを利用できるSaaS型の、大きく2パターンが考えられます。
ネット上で利用できるITサービスやクラウドサービスとして提供されるものはSaaS型であり、利用者は月額料金や従量課金制などの方式で利用料を支払います。
販売形式はサービスの売り方や利用料の決定へ大きく関与するポイントです。
自社サービスの優位性や差別化
自社サービスが競合他社のサービスと比較してどのような優位性を確保できているのか、客観的に把握しておくことも欠かせません。
競合サービスとの差別化はユーザーへアピールできるポイントになる上、希少性という付加価値を値段設定に反映する際にも重要です。一方、類似のITサービスが市場にあふれている場合、必然的に価格設定を考える場合にも抑えるべきといった方向性が見えてくるでしょう。
ITサービスの価格戦略・値段設定が難しい理由
実際に形を持っている商品を販売することに対して、ITサービスの価格戦略や値段設定は難しくなりやすい傾向があります。ここではITサービスの価格戦略の構築が難しくなってしまう理由についてまとめていますので、自社のサービスと照らし合わせてみましょう。
価格戦略の基本的な考え方が異なる
一般的な価格戦略では、企業が提供するサービスや商品を顧客が購入することを前提としており、BtoCをベースとしたプランが構築されています。
しかしITサービスでは消費者向けのサービスだけでなく、企業向けのBtoBサービスを提供している場合も少なくありません。そのため、一般消費者を対象とした価格戦略をそのまま当てはめにくいことがポイントです。
正確な原価が分かりにくい
例えば商品を製造するために資材や原料を購入して、生産ラインを稼働させているような場合、資材や原料の購入費や、生産ラインのランニングコストといった費用をそのまま計算することが可能です。
対するITサービスの場合、原価の多くがエンジニアの労務費になっており、さらに作業前の見積額と実際の作業で発生した工数(コスト)で差が生じることも少なくありません。そのため正確な原価計算を行いにくく、値段設定を難しくする理由になっています。
IT企業が価格戦略を策定するメリット
価格戦略を定めることなく値段設定を行う場合、常に場当たり的な価格設定をしなければならず、安定した利益率を確保したり、事業戦略として利益をシミュレーションしたりしていくことが困難となります。そのため、IT企業が自社の特性や適性を反映させた価格戦略を策定することは、企業としての事業安定性やコストメリットを追求していく上で重要です。
また、あらかじめ価格戦略を構築しておくことで、今後に新たなITサービスを提供する際にも価格設定を明確化しやすくなり、企業としての他の事業戦略と合わせて総合的なプランニングを進められることもメリットです。
まずは正確な原価を把握することが重要
価格戦略を実践していくためにも、まずは対象となるITサービスについて正確な原価やコストの内容を把握していくことが不可欠となります。
原価を把握するには、ITサービスやシステムの構築に携わったエンジニアの労務費を具体的に計算したり、また作業環境を維持するために発生しているコストを試算したりと、複数のポイントに着目してトータルコストを考えていかなければなりません。
なお、作業環境の維持にかかっているランニングコストは、他のサービスとまたがって発生している場合もあり、按分の仕方などに関して基準を定めることも肝要です。
正確に原価を把握することで得られるメリット
コストの適正性を見直して原価率を下げられる可能性がある
実際にかかっている原価やコストを明確化できれば、同時に節約できるポイントや無駄が多いと考えられるポイントを発見しやすくなります。
必要なコストと、削減できるコストをしっかり区別することで無駄を省きやすくなり、原価率を抑えて利益率の向上を目指していくための戦略も立てやすくなるでしょう。
正確な情報にもとづいて意思決定できるようになる
正確な原価を知ることで、価格戦略や事業戦略をプランニングしていく際にもアイデアや方針に明確な論拠を持たせることが可能となります。
論拠薄弱な戦略は客観性に欠けたり、場当たり的な対応によって統一性を維持させることが困難になったりします。
また、正確な情報にもとづいて意思決定をすることで、一時的に想定外の状況へ陥ったとしても自信を持ってサービスを維持できるようになることも重要です。
IT企業の原価管理にはプロジェクト収支管理ツールの導入がおすすめ
プロジェクト収支管理ツールを導入することで、ITサービスの提供や作業工程に関して自動的に収支計算を行ったり、原価の分類を簡便化したりといったメリットを得られます。
そもそも価格戦略の構築や値段設定が難しいITサービスだからこそ、プロジェクト収支管理ツールのようなサポート環境を構築して原価管理を適正化する価値も高まっていきます。
ただしプロジェクト収支管理ツールにも様々なものがあり、自社のニーズやサービス内容にマッチした製品を選択することが大切です。
業界に特化した
プロジェクト収支管理
ツール2選
案件ごとの収支管理をする機会が多い業界・業種に特化したツールを使うことで、
ストレスなく痒い所に手が届く利用が実現できるでしょう。
こでは、プロジェクト収支管理ツール19社を調査し、業界に特化したおすすめツールを選出しました。
プロカン
主な機能
- 承認ワークフローがクラウド上で可能
- 各種稟議書の電子決裁可能
- シンプルで使いやすいUI
- 電子帳簿保存法改正、インボイス制度にも完全対応
| スタンダード |
4,400円/月(税込)
(1アカウントあたり) |
| プロ |
4,950円/月(税込)
(1アカウントあたり) |
ZAC
主な機能
- 勤怠などの各種収支をモニタリング
- タスクをシステム上で共有
- 販売、購買、工数、経費、在庫管理もできる総合ERP
- MTGへの参加依頼可能
| 一括ライセンス買取型 |
要問合せ |
| 月額ライセンス利用型 |
要問合せ |
選定基準
2023年4月19日時点で、Googleで「プロジェクト収支管理」と検索して
公式サイトを確認できた19ツールの中から、下記条件に当てはまるツールを紹介しております。
- 公式サイトにサービス費用が明記されている
- 公式サイトで特定の業界に向けてのツールであると明記されている